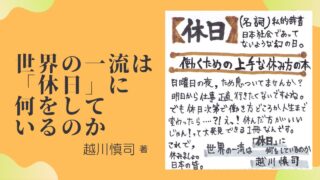|
|
目次
「きっかけ」…なぜ読み始めたか?
2024年年末に、書店でよく目にするタイトルだったからです。
2024年11月14日映画版も公開されていましたね。
辻村深月さんは、私のお気に入りの作家さんの一人です。
ミステリーの話の展開もありながら、本文の中に主人公の瑞々しい感性が随所にあり、鋭い着眼点にハッとさせられて、読んでいてとても興味深いのです。
私は「太陽の坐る場所」(2015年)で、初めて辻村さんの作品を読み始めました。

そして本屋大賞に選ばれた有名作品「かがみの孤城」(2017年)が面白すぎて、夜眠ることも忘れて、一気に読み進めました。
その辻村さんが書いたこの本が、2024年に映画化されたというので、どんな内容なんだろうと興味をそそられて読み始めました。

「学び」…この本で学べること
小説の良いところは、私は次の3点だと思っています。
1.登場人物の人生をそのまま追体験できる。
2.登場人物の感性や思考がダイレクトに頭に入ってくる。
3.自分の人生、価値観、性格を内省することができる。
これは中々、自己啓発本では学べないことだと思います。
知識をインプットすることを第一とするのではなく、小説からは、こんな人生だったら自分だったらどう思うか、登場人物と照らし合わせて自分の価値観はどうなっているのか、と考えることができるのです。
それらを踏まえて、この本でとても勉強になった次の3点をご紹介しますね。
かっこつけても、完璧にかっこつけられない
一番、私が本書で学んだことは、本当の自分の姿はいずれ分かる人には分かるから、かっこつけずに生きたほうがいい、ということです。
特に登場人物の真実(まみ)の生き方が、痛いほどにそれを教えてくれています。
真実の不器用な生き方がゆえに、婚約している真実に付きまとうストーカーの存在があり、そして真実はある日、婚約者の架(かける)と結婚間近でありながら、突然失踪してしまうのです。
本書の前半は、結婚という人生の大きな選択をするために、30代の男女が婚活やマッチングアプリをして、どのように相手に出会ったのかという部分が語られています。
登場人物の架と真実も、結婚することを目的に、マッチングアプリをしていた30代の男女です。
物語が進んでいくにつれて、登場人物の本当の姿、過去と嘘が次第に分かっていきます。
もっと、自然体でカッコつけない自分を、親・姉妹・友人・同僚に見せられていたら、違う人生を送れていたのではないか…と、私は読みながら考えていました。
私は周囲の目や、社会での自分のランク付けみたいなものを、自分で勝手に気にしてしまうクセがあります。
周囲と比べて…と考えると、つい良い恰好をしたり、背伸びをして、自分をよく見せたがってしまうんですよね。
しかし、それは本来の自分を隠しているにすぎず、果たして周りの人が本来の自分を受け入れてくれるのかどうか、大きな不安に後々つながってくるのです。
本書を読んでいると、自分を周りによく見せたい私の性格をそのまま写しているように思えたのです。
読み進めていくうちに、自分自身の格好つけたい性格を、鏡で写されているような不思議な感覚になります。
昨今のSNSが当たり前の社会では、他人から見て、ダサくない、人並みより少し上の幸せな毎日を送れている自分を意識してしまうのではないかと思いました。

自分をそのまま愛してほしいのであれば、かっこつけずに、たとえかっこ悪いところも全て見せたほうがいい、と本書から学ぶことができました。
善良が最良ではない
この本に登場する人物は、皆それぞれ、その人なりの「善良さ」をもっています。
「善良さ」とは、ポリシーであり、今まで生まれ育ってきた環境の中での常識のようなもの、だと私は感じました。
それぞれ人には大切にしている自分の「善良さ」があり、それを守るがゆえに、偏見や独断という狭い判断をしてしまいがちなのかもしれません。
架は、自分なりに自分の人生に必死で、自分は恋人も満足させているという思いがあり、
真実は、親や周りの人の忠告をきっちり守る正しい人物として生きてきたという自負があります。
架の悪友の美奈子は、自分は架をずっと見守ってきた親友という善良さがあり、
真実の母の陽子は、母親として真実の人生を不安や心配から遠ざけようと努力してきたという善良さがあります。
「私は~してきたのに」という善良さがあると、人間はそれで他人を攻撃したり、自分の善の部分を誇示してしまうのかな、と思いました。
しかし、それは一個人の独りよがりでもあり、善良さは決して最良ではないのですよね。
あくまでも、自分の狭い世界の中での善良さであり、その善良さで他人を変えたり、支配ができないことに気が付けません。
私は、自分はどんな善良さを持っているのだろうか、そしてそれをどんな時に誇示してしまうのだろうか、と考えて、猛烈に恥ずかしくなり、反省してしまったのです。
善良さを盾にしてしまう自分がとても人間臭いな、と恥ずかしくなりました。
登場人物の姿から自分を照らし合わせて、内省できるというのが、小説の良いところだと思います。

自然体になれたとき、人は強くなれる
本書の後半は、過去と登場人物の本当の姿が明らかになった後、どうこれから人生を生きていくのか、というプロセスが描かれています。
自分は人生をどう生きるか、周囲の人たちといかに関係を築いていくのか、という答えを探していくようなストーリーです。
後半で一番目を見張るのは、真実の成長と変化でしょうね。
自分で選択をして、経験をしていくにつれて、新しい世界に触れて、真実の内面が変化をしていくのです。
多くの発見と体験が、本当の彼女を蘇らせていきます。
自分で選んで行動をしていくうちに、自分も他の人も分からなかった、本当の自分の姿に対面していくのです。
私は、この後半の展開がものすごく好きで、自分の中で癒しを感じました。
真実が最初の自己評価も自己肯定感も低くて、なぜ生きているのか分からない状態から、人間として生きる喜びを感じる過程が、そのまま自分にエールをくれているように感じたのです。
内面の変化と成長を描いているストーリーとして、ジブリ映画の「千と千尋の神隠し」や「魔女の宅急便」の後半部分にも、通じるところがあるな、と私は感じています。


主人公がいろんな体験をして、自分の変化に驚き、成長をしていくというところを描いているように思います。
エピローグに私は感動してしまい、4回も読み直しました。
人はこんなにも変わることができるのか、と泣きそうになりました。
私も自分を変えることができる、そしてこれからの人生がたとえ不確定でも歩めるのではないか、と思うことができたのです。
大きな勇気をもらえました。
本書を通して、自分が励まされているような感覚を覚えました。

「処方箋」…こんな時にぴったり
・ありのままの自分が分からなくなったとき
・人間関係の中でウソがつけなくなったとき
・婚活や結婚への固定観念に苦しくなった時
・周囲の目が気になって疲れたとき
前半は、きっと人によっては自分を見ているかのような、耳の痛い話かもしれません。
しかし、前半で自分自身に向き合ってから、後半のストーリーを読むと、ものすごい感動を味わえて、勇気が湧いてくる優しい物語です。
最後に
私が辻村さんの作品から、なんだか目が離せないのは、作品の最後に必ず「救い」があると思っているからなんです。
それぞれの人生で我慢してきたこと、辛かったことを抱えてきた登場人物が、作品のできごとを通じて、最終的には良い方向へ変わることができる「救い」を描いているように感じます。
辻村さんの作品の「かがみの孤城」、「琥珀の夏」でも、それは共通しているように思います。


辻村さんの作品の魅力は、登場人物の瑞々しい感性をちりばめた語り方です。
辻村さんの作品を読むと、私は、普段に押し隠している人間としての感受性を蘇らせることができるような、癒される感覚になります。
辻村さんの作品がこんなにもベストセラーになるのも、きっと多くの人の感性を蘇らせるものなのだと思います。
その人気は、多くの人たちが普段は他人には言えない痛みや苦しみを抱えながら、必死に生きている証なのかなと感じました。
毎日の中で、ゆっくりする時間を作って、心の栄養剤のかわりに読みたい作家さんの一人です。
|
|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/43dfbf37.9fe21bd4.43dfbf38.56389578/?me_id=1213310&item_id=20740604&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fbook%2Fcabinet%2F0597%2F9784022650597_6_6.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)